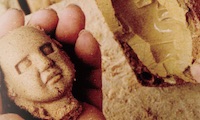雛人形はいつから飾るの?いつまでに片付けるといいの?
お子様の健やかな成長と幸せになってほしいとの家族の願いを込めて贈るひな人形。
あたたかな春を感じ、きれいな雛人形と一緒にお祝いをします。
でも、雛人形っていつから飾りいつまでに片付ければいいの?と疑問に思う方も多いと思います。
こちらでは、
・雛人形はいつまでに飾りいつまでに片付けるの?
・雛人形を購入する時期
・雛人形を飾る意味と何歳まで雛人形を飾るの?
という様々な基礎知識についてご紹介しています。
雛人形はいつから飾るの?

雛人形は、一般的には、春の始まりの立春(節分の翌日)ごろから2月の中旬ごろまでに飾ることが多いです。
桃のお節句ということもあり、春の訪れを告げる頃に飾られることが多いということではないでしょうか。
ただ、雛人形を飾る時期に明確な決まりはありませんので、早く出す分には全く問題はありません。
1月の上旬ごろからお飾りいただいても構いません。
もちろん、3月3日にお飾りいただいても良いのですが、長く雛人形を楽しむために、早めに飾るのが良いでしょう。
- ・雨水に飾ると良縁につながる?
地域によっては、二十四節気のひとつ、雨水(うすい)に飾るとよいと言われるところもあります。
雨水は、毎年2月18日、19日にあたる、温かさに雪や氷が溶けて雨水として降り注ぐ日です。
昔から、農耕の準備をはじめる目安としてつかわれてきました。
また、水は命を象徴する源とも言えます。
水神の弥都波能売神(みつはのめのかみ)は、豊穣をもたらす農耕神とされ、子宝や安産の神とも信仰されています。
このようなこともあり、雨水の日に雛人形を飾ることは、良縁につながるという逸話もあります。
雛人形は誰が飾る?
雛人形を飾るのは、一般的には家族全員で行うことが多いです。
特に、女の子の健やかな成長と幸せを願って、母親や祖母が中心となって飾ることが一般的です。
家族全員で協力して飾り付けを行うことで、家族の絆を深めるとともに、子供の成長を祝う大切な行事となっています。
初めて雛人形を飾る際の注意点
初めて雛人形を飾る際は以下のことに気をつけるとよいでしょう。
- 飾る場所
直射日光が当たらない場所を選びましょう。日光は人形の色褪せの原因になります。
エアコンの吹き出し口の下も避けてください。温度変化や湿気が人形に悪影響を与える可能性があります。
- 準備
飾る前に手をきれいに洗い、白手袋を着用しましょう。手油やほこりが人形に付着するのを防ぐためです。
飾り台や屏風、お道具を確認し、必要なものが揃っているかチェックしておくとスムーズです。
- 飾り付けの順序
飾り台(段)、屏風、お道具、人形の順に飾ります。
小道具は人形に持たせる前に確認し、丁寧に取り扱いましょう。
特に壊れやすいものは慎重に扱ってください。
- 写真を撮る
初めて飾る際には、元の収納状態に戻すために写真を撮りながら作業を進めると良いでしょう。
これらの注意点を守ることで、雛人形を美しく保ち、長く楽しむことができます。
雛人形はいつまでに片付ければいいの?

雛人形は、3月3日のひな祭りまで飾る場合が一般的ですが、旧暦(4月3日)まで飾る地域もあります。
雛人形は、3月3日が終わったらすぐに片付けないといけないというわけではありません。目安としては、3月の中旬ごろまでに片付けをすると良いでしょう。旧暦で飾る場合は、4月の中旬ごろまでを目安とし、天気の良い日にしまってください。
片付けが遅くなると「お嫁に行けなくなる」と心配をされる方もいらっしゃるかもしれませんが、それは、「片付けができる立派な女性になってほしい」という意味ですので、あまり気にしないでください。
- ・雛人形を天気の良い日に片付ける理由
雛人形は、湿気を含んだままの状態でしまうと、シミやカビの原因になりますので天気が良く空気の乾いた日にお片付けをしてください。
お人形はとてもデリケートなものですので、お顔や手に直接触れないようにしてください。指紋が付着する原因となります。
ホコリを良くはたき、防虫剤を少なめにし、極度に乾燥したり、湿気の多いところは避けてしまってください。
雛人形の収納方法について詳しく知りたい方は
「雛人形の収納方法を写真と一緒にわかりやすく解説! 味岡人形 映水ブログ」を参考にしてください。
- 迷ったら啓蟄の日に片付けましょう
雛人形を片付ける日に迷った場合、啓蟄(けいちつ)の日に片付けるのが良いとされています。
啓蟄は、二十四節気の一つで、毎年3月5日頃にあたります。
この日は、冬眠していた虫が春の訪れを感じて土の中から出てくる時期を意味します。
雛人形を出すのに良い日とされる「雨水(うすい)」の次の節気が啓蟄です。
季節の移り変わりに合わせて片付けることで、自然のリズムに従った行動となります。
また、啓蟄の頃は、気温が上がり湿気が少なくなるため、雛人形を片付けるのに適した時期です。
湿気が少ない日は、カビや虫の被害を防ぐことができます。
雛人形を片付ける際には、晴れた日を選び、湿気対策をしっかりと行いましょう。
これにより、雛人形を長く美しく保つことができます。
雛人形のお手入れ方法と頻度
雛祭りが終わったらすぐにお手入れをするのがおすすめです。湿気の少ない晴れた日に片付けると、長期間の保存でも人形の状態を保てます。
長期間収納している場合、湿気がこもらないよう9~10月ごろに一度箱から出して風を通すと良いです。
白手袋、柔らかい筆や毛ばたき、乾いた柔らかい布、防虫剤(人形専用)、乾燥剤などを用意します。
雛人形や飾り台に付いたホコリを、毛ばたきや柔らかい筆で優しく払い落とします。顔など細かい部分には新品の筆を使うと効果的です。
触る際は、手の油分が付くとシミや汚れの原因になるため、白手袋を着用してお手入れします。
衣装に汚れやシワがないかチェックします。汚れがある場合は、乾いた柔らかい布で優しく拭き取ります。
顔は和紙やティッシュで軽く包み、髪や衣装が傷つかないようにしてから箱に収めます。
また、防虫剤を入れる場合は人形専用のものを使用してください。
雛人形の保管方法
雛人形を保管する際におすすめの入れ物を3つ紹介します。
- 購入時に入っていたダンボール
購入時に使われたダンボール箱はサイズがぴったりで、手軽に利用できます。
専用の仕切りや緩衝材が付いている場合が多く、安全に保管できます。
ただし、ダンボールは湿気や虫害に弱いため、乾燥剤を入れると良いでしょう。
また、湿度の高い場所での保管は避けることが重要です。
- 桐箱
桐の素材は湿気に強く、防虫効果があるため、雛人形の保管に非常に適しています。
高級感があり、長期間の保存でも人形を美しく保つことができます。
他の収納方法に比べて少し値段が高いですが、大切な雛人形を保護するには最適です。
- プラスチックケース
軽量で扱いやすいのが魅力です。透明タイプの場合、中身が見えるため便利です。
湿気や虫から守ることができ、耐久性が高い点も利点です。
完全密閉型の場合は適度に湿度を調整するために乾燥剤を使用しましょう。
雛人形をしまう場所
雛人形をしまう際には、その繊細さを守るために適した環境を選ぶことがとても大切です。
- 湿気が少なく乾燥しすぎない場所を選ぶ
雛人形は湿気に弱く、カビや変色の原因となることがあります。
一方で、乾燥しすぎる場所では、素材が割れたり縮んだりするリスクがあります。
理想的な湿度は50~60%ほど。
湿気の多い場所には乾燥剤を、乾燥が強い場所には加湿器を活用して調整してください。
- 直射日光や強い光を避ける
日光が当たると、雛人形の顔料が色あせたり、生地が劣化することがあります。
窓際や日光が当たりやすい場所は避け、暗くて安定した明るさを保てる収納スペースを選ぶと良いです。
- 温度変化が少ない環境を保つ
寒暖差が激しい場所では、結露が発生してカビや劣化の原因になる可能性があります。
外壁に面していないクローゼットや押し入れの上段が最適です。
雛人形を床近くに置くと、ホコリが溜まりやすく湿気の影響も受けやすくなります。
収納は押し入れの上段や棚の高い位置を選ぶと安心です。
- 定期的に風を通す
保管中の箱の中は湿気がこもりやすいため、年に一度ほど晴れた日に箱を開けて風を通すのがおすすめです。
梅雨明けや秋晴れの時期が最適です。
雛人形を購入する時期
雛人形を買う時期は、もちろん直前でも構いません。
ただ、お店によっては早期の注文には特典が付いている場合もあります。
お気に入りの雛人形を選ぶ際には、お顔や衣装はもちろん、台や屏風も組み合わせて選ぶことができる場合が多くあります。
また、オーダーメイドの雛人形の場合、お顔や衣装を制作するために1カ月から2カ月ほど掛かる場合もあります。人気のお人形は、直前には、混み合う場合もあるかもしれません。時間に余裕を持ったご注文が安心です。
雛人形を飾る意味

雛人形は、平安時代に紙で作られた小さなお人形の「ひとがた」に自分の息を吹きかけて身に降りかかる災厄を移し、川や海に流したことに由来していると言われています。
さらに、赤ちゃんが元気で健やかに育つようにと枕もとに「天児(あまがつ)や、「這子(ほうこ)」を身代わりの意味として置くという風習も平安貴族のあいだでは盛んに行われていました。
天児(あまがつ)とは、絹で作られており、まるいお顔に目、鼻、口が描かれ、白い衣装が着せられているお人形です。
這子(ほうこ)も絹で作られており、まるいお顔に目、鼻、口が描かれ、黒い絹の髪の毛が付けられ、胴は、ぬいぐるみのような作りになっているお人形です。
「あまがつ」と「ほうこ」のどちらのお人形も幼児に降りかかる災厄を負わせる身代わりの意味があるとされていました。
そして時代が進み、「川や海に流されること」から「室内に飾る」こととなり、室町時代の終わりごろには、立雛ができあがり、江戸時代にはいろいろな雛人形が誕生しました。
雛人形が身代わりとなることで災厄を祓い、赤ちゃんの健やかな成長を願うおまもりとして飾られています。
雛人形は何歳まで飾るの?

雛人形を何歳まで飾るのか、ということは、実は明確に決められてはいません。
お子様が健やかに育つことにより、願いが叶い、雛人形のお役目が終わることとなります。
雛人形のお役目が終わったからといって、雛人形を飾ってはいけないということもありません、一生お飾りいただいても構いません。
女の子が生まれた際には、赤ちゃんの雛人形の横にお母さんの雛人形も一緒に飾るということも良いことです。
実家の両親の家に飾るということも良いと思います。
どうしてもお別れをすることをご希望の方は、お寺などで人形供養という形で、お人形に「ありがとう」の気持ちを込めてお別れをするという方法もあります。
まとめ
雛人形は、春の始まりの立春の頃に飾り、3月3日の雛祭りが終わったら天気の良い日にお片付けをするという流れが一般的です。
ただ、雛人形を早く飾る分には全く問題はありませんので、1月の10日ごろから飾り、長く楽しむこともおすすめです。
また、大切な雛人形を一生お飾りいただくことも、毎年美しい季節を感じていただけると思います。
雛人形は、かわいいお子様の一生のお守りとなる大切な日本の伝統文化です。
- 投稿日時:2025.7.07 08.53.27 / カテゴリー:コラム
- https://ajioka.net/blog/colunm/20330