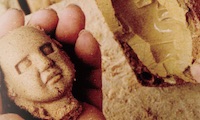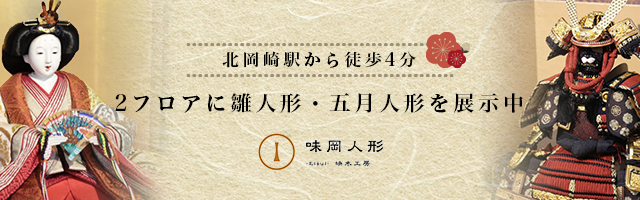ひな祭りに飾るぼんぼりの意味とは?どの位置に飾ればいいの?
雛人形の両脇に飾られているちょうちん型をしたお道具の「ぼんぼり」。
「うれしいひなまつり」の歌にも
「あかりをつけましょ ぼんぼりに」と登場しますが、ぼんぼりとは何か、雛人形に飾られている意味を詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、ぼんぼりの雛飾りにおける意味や飾る位置などについて解説します。
雛人形の両脇に飾られている「ぼんぼり」とは?
ぼんぼりとは小型の行灯の一種で、手燭(てしょく)や燭台に紙や布を張り、その中でろうそくを用いて点灯するものです。
まだ電気のなかった時代に、照明器具として用いられていました。
ぼんぼりという名前の由来には諸説あります。
一説では紙や布を通したほんのりとした明かりの「ほんのり」が変化してぼんぼりと呼ばれるようになったとされています。
本来のぼんぼりの意味が「ぼんやりとしていてはっきりしないさま」「ものの色や形がぼやけて見えるさま」であったことも関係しているようです。
ちなみに、ぼんぼりの漢字表記である「雪洞」は、ぼんぼりの形状や構造が茶道で用いられる「雪洞(せっとう・木や竹に薄い紙を張った蓋付きの道具)」に似ていることから同じ漢字を当てるようになったと言われています。
その一方で、雪で作ったかまくらの中で火を灯した際に、そのやわらかな明るさがぼんぼりの灯りに似ていたことに由来するという説もあります。
雛人形にぼんぼりが飾られる意味
ぼんぼりは多くの雛人形に飾られていますが、その背景には「江戸時代の結婚式の風習」が大きく関係しています。
「あかりをつけましょ ぼんぼりに」と歌に出てくるように、なぜお雛様にぼんぼりの灯りが必要だったのかというと、
雛人形は天皇の結婚式を模したものですが、雛人形文化が大衆に広まった江戸時代当時の結婚式は現代のような日中ではなく「亥の刻(21時から23時の間)」に行われていました。
その時間帯は灯りがなければ何も見えないため、ぼんぼりは結婚式における必須アイテムだったようです。
その風習がいつしか雛人形にも取り入れられるようになり、お人形の周辺を彩るお道具のひとつとして今もなお親しまれています。
雛人形のぼんぼりはどこに飾ればよい?電球はずっと点けておく?
雛人形にはぼんぼり以外にも付属品が多いので、ぼんぼりをどこに飾るか迷うかもしれません。
特に段のある雛飾りの場合は、どの段に飾るか迷うのではないでしょうか。
結論からお伝えしますと、段数によってぼんぼりを飾る場所は変わりません。
ぼんぼりは「男雛と女雛が飾られている段の左右」に飾りましょう。
ぼんぼりによって模様やデザインが前後で異なるものもあるので、他の道具や人形とのバランスを見ながら、おしゃれに見える角度を探して配置してみてください。
また、雛人形のぼんぼりには点灯可能なものが多く、近年では電池で光るタイプやコンセントタイプ、LED、電球などバリエーションが豊富です。
ぼんぼりは雛人形を飾っている間ずっと点灯させておいても良いですが、電気代等が気になる方はこまめに消してもいいでしょう。
ぼんぼりが点灯しなくなったらどうすればいいの?
「ぼんぼりが点灯しなくなってしまった」というのはよくあるトラブルです。
この原因として、乾電池の液漏れが最も多いです。
ぼんぼりを保管する際は必ず乾電池を抜いて保管してください。
また、ぼんぼりの電球は交換することができます。
ぼんぼりの電球はソケットタイプの場合はほとんどですので、LEDにしたい場合はソケットタイプのLEDに変えることで可能です。
まとめ
ぼんぼりは夜間に行われる結婚式の照明器具であったことから、天皇の結婚式を模した雛人形における大切なお道具の一つとなっています。
男雛と女雛のお顔がぼんぼりの灯りによってほのかに照らされるように飾ってあげてくださいね。
当工房では、江戸時代から続く伝統技術で雛人形を作成しています。
雛人形は、大切なお子様の健やかな成長と幸せを願い、お守りとなる日本の伝統文化です。
お気に入りの雛人形を飾り、お子様の誕生を家族で毎年お祝いしていきましょう。
- 投稿日時:2023.3.15 21.40.53 / カテゴリー:コラム
- https://ajioka.net/blog/colunm/35656